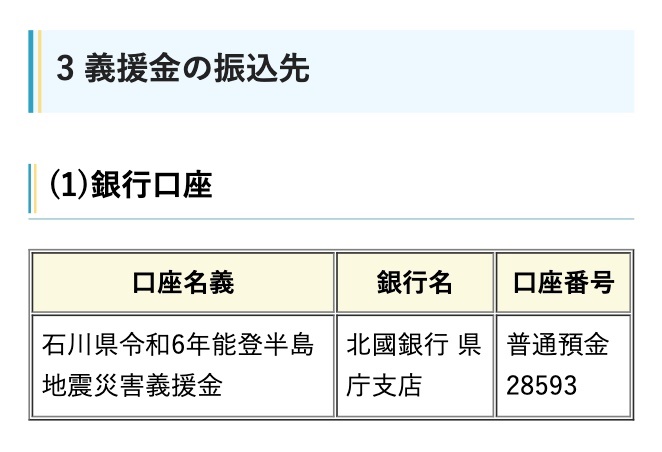| 26 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 切土工は、斜面を構成している不安定な土層や土塊をあらかじめ切り取る、あるいは斜面を安定な勾配まで削り取る工法である。
2. グラウンドアンカー工は、表面の岩盤が崩落又ははく落するおそれがある場合や不安定な土層を直接安定した岩盤に緊結する場合などに用いられる。
3. コンクリート張工は、斜面の風化や侵食、岩盤の軽微なはく離や崩落を防ぐために設置され、天端及び小口部は岩盤内に水が浸入しないように地山に十分巻き込むことが重要である。
4. もたれ式コンクリート擁壁工は、斜面崩壊を直接抑止することが困難な場合に斜面脚部から離して設置される擁壁である。
|
もたれ式コンクリート擁壁工は、斜面崩壊を直接抑止することが困難な場合に斜面脚部から離して設置される擁壁である。
|
| 27 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
道路のアスファルト舗装における路床の安定処理の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 安定材を散布する場合は、散布に先立って現状路床の不陸整正や、必要に応じて仮排水溝の設置などを行う。
2. 安定材の混合は、散布終了後に適切な混合機械を用いて所定の深さまで混合し、混合中は深さの確認を行い、混合むらが生じた場合は再混合する。
3. 安定材に粒状の生石灰を使用する場合は、一回目の混合が終了したのち仮転圧し、生石灰の消化(水和反応)が終了する前に再度混合し転圧する。
4. 安定材の散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合は、防塵型の安定材を用いたり、混合機の周りにシートの設置などの対策をとる。
|
安定材に粒状の生石灰を使用する場合は、一回目の混合が終了したのち仮転圧し、生石灰の消化(水和反応)が終了する前に再度混合し転圧する。
|
| 28 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
道路のアスファルト舗装における上層路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 石灰安定処理工法は、骨材中の粘土鉱物と石灰との化学反応により安定させる工法であり、セメント安定処理工法に比べて強度の発現が早い。
2. セメント安定処理工法は、骨材にセメントを添加して処理する工法であり、強度が増加し、含水比の変化による強度の低下を抑制できるため耐久性が向上する。
3. 粒度調整工法は、良好な粒度になるように調整した骨材を用いる工法であり、敷均しや締固めが容易である。
4. 瀝青安定処理工法は、骨材に瀝青材料を添加して処理する工法であり、平坦性がよく、たわみ性や耐久性に富む。
|
石灰安定処理工法は、骨材中の粘土鉱物と石灰との化学反応により安定させる工法であり、セメント安定処理工法に比べて強度の発現が早い。
|
| 29 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
道路のアスファルト舗装における表層及び基層の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. アスファルト混合物の敷均しは、使用アスファルトの温度粘度曲線に示された最適締固め温度を下回らないよう温度管理に注意する。
2. アスファルト混合物の二次転圧は、適切な振動ローラを使用すると、タイヤローラを用いた場合よりも少ない転圧回数で所定の締固め度が得られる。
3. 締固めに用いるローラは、横断勾配の高い方から低い方へ向かい、順次幅寄せしながら低速かつ一定の速度で転圧する。
4. 施工の継目は、舗装の弱点となりやすいので、上下層の継目が同じ位置で重ならないようにする。
|
締固めに用いるローラは、横断勾配の高い方から低い方へ向かい、順次幅寄せしながら低速かつ一定の速度で転圧する。
|
| 30 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. オーバーレイ工法は、既設舗装の上に、厚さ3cm以上の加熱アスファルト混合物層を舗設する工法である。
2. 切削工法は、路上切削機械などで路面の凸部などを切削除去し、再生用添加剤を加え再生した表層を構築する工法である。
3. 薄層オーバーレイ工法は、既設舗装の上に、厚さ3cm未満の加熱アスファルト混合物を舗設する工法である。
4. パッチング及び段差すり付け工法は、ポットホール、くぼみ、段差などを加熱アスファルト混合物や常温混合物などで応急的に充てんする工法である。
|
切削工法は、路上切削機械などで路面の凸部などを切削除去し、再生用添加剤を加え再生した表層を構築する工法である。
|
スポンサー
|
| 31 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
排水性舗装に使用するポーラスアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. タックコートは、舗設するポーラスアスファルト混合物層とその下層との接着をよくするために、原則としてゴム入りアスファルト乳剤を使用する。
2. 敷均しは、通常のアスファルト舗装の場合と同様に行うが、温度の低下が通常の混合物よりも早いためできるだけ速やかに行う。
3. 初転圧及び二次転圧は、ロードローラを用いた締固めにより所定の締固め度を確保する。
4. 仕上げ転圧には、表面のきめを整えて、混合物の飛散を防止する効果を期待して、振動ローラを使用する。
|
仕上げ転圧には、表面のきめを整えて、混合物の飛散を防止する効果を期待して、振動ローラを使用する。
|
| 32 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
道路のコンクリート舗装のセットフォーム工法による施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. コンクリート版の表面は、水光りが消えるのを待って、ほうきやはけを用いて、すべり止めの細かい粗面に仕上げる。
2. 隅角部、目地部、型枠付近の締固めは、棒状バイブレータなど適切な振動機器を使用して入念に行う。
3. 横収縮目地に設ける目地溝は、コンクリート版に有害な角欠けが生じない範囲内で早期にカッタにより形成する。
4. コンクリートの敷均しは、材料が分離しないように、また一様な密度となるように、レベリングフィニッシャを用いて行う。
|
コンクリートの敷均しは、材料が分離しないように、また一様な密度となるように、レベリングフィニッシャを用いて行う。
|
| 33 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
ダムの基礎掘削に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 基礎掘削は、掘削計画面より早く所要の強度の地盤が現れた場合には掘削を終了し、逆に予期しない断層や弱層などが現れた場合には、掘削線の変更や基礎処理を施さなければならない。
2. 掘削計画面から3m付近の粗掘削は、小ベンチ発破工法やプレスプリッティング工法などにより施工し、基礎地盤への損傷を少なくするよう配慮する。
3. 仕上げ掘削は、一般に掘削計画面から50cm程度残した部分を、火薬を使用せずに小型ブレーカや人力により仕上げる掘削で、粗掘削と連続して速やかに施工する。
4. 堤敷外の掘削面は、施工中や完成後の法面の安定性や経済性を考慮するとともに、景観や緑化にも配慮して定める必要がある。
|
仕上げ掘削は、一般に掘削計画面から50cm程度残した部分を、火薬を使用せずに小型ブレーカや人力により仕上げる掘削で、粗掘削と連続して速やかに施工する。
|
| 34 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
ダムのコンクリートの打込みに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. RCD用コンクリートの練混ぜから締固めまでの許容時間は、ダムコンクリートの材料や配合、気温や湿度などによって異なるが、夏季では5時間程度、冬季では6時間程度を標準とする。
2. 柱状ブロック工法でコンクリート運搬用のバケットを用いてコンクリートを打込む場合は、バケットの下端が打込み面上1m以下に達するまで下ろし、所定の打込み場所にできるだけ近づけてコンクリートを放出する。
3. RCD工法は、超硬練りコンクリートをブルドーザで敷き均し、0.75mリフトの場合には3層に、1mリフトの場合には4層に敷き均し、振動ローラで締め固めることが一般的である。
4. 柱状ブロック工法におけるコンクリートのリフト高は、コンクリートの熱放散、打設工程、打継面の処理などを考慮して0.75〜2mを標準としている。
|
RCD用コンクリートの練混ぜから締固めまでの許容時間は、ダムコンクリートの材料や配合、気温や湿度などによって異なるが、夏季では5時間程度、冬季では6時間程度を標準とする。
|
| 35 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
山岳トンネルの掘削の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 全断面工法は、小断面のトンネルや地質が安定した地山で採用されるが、施工途中での地山条件の変化に対する順応性が低い。
2. 側壁導坑先進工法は、側壁脚部の地盤支持力が不足する場合や、土被りが小さい土砂地山で地表面沈下を抑制する必要のある場合に適用される。
3. 補助ベンチ付き全断面工法は、ベンチをつけて切羽の安定をはかるとともに、掘削効率の向上をはかるために、上部半断面と下部半断面の同時施工を行う。
4. ベンチカット工法は、一般に上部半断面と下部半断面に分割して掘削する工法であり、地山が不良な場合にはベンチ長を長くする。
|
ベンチカット工法は、一般に上部半断面と下部半断面に分割して掘削する工法であり、地山が不良な場合にはベンチ長を長くする。
|
スポンサー
|
| 36 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
山岳トンネルの覆工コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 覆工コンクリートの打込み時期は、掘削後、支保工により地山の内空変位が収束した後に施工することを原則とする。
2. 覆工コンクリートの打込みは、型枠に偏圧が作用しないように、左右に分割し、片側の打込みがすべて完了した後に、反対側を打ち込む必要がある。
3. 覆工コンクリートの背面は、掘削面や吹付け面の拘束によるひび割れを防止するために、シート類を張り付けて縁切りを行う必要がある。
4. 覆工コンクリートの型枠の取外しは、打ち込んだコンクリートが自重などに耐えられる強度に達した後に行う必要がある。
|
覆工コンクリートの打込みは、型枠に偏圧が作用しないように、左右に分割し、片側の打込みがすべて完了した後に、反対側を打ち込む必要がある。
|
| 37 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
離岸堤に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 砕波帯付近に離岸堤を設置する場合は、沈下対策を講じる必要があり、従来の施工例からみればマット、シート類よりも捨石工が優れている。
2. 開口部や堤端部は、施工後の波浪によってかなり洗掘されることがあり、計画の1基分はなるべくまとめて施工することが望ましい。
3. 離岸堤は、侵食区域の下手側(漂砂供給源に遠い側)から設置すると上手側の侵食傾向を増長させることになるので、原則として上手側から着手し、順次下手に施工する。
4. 汀線が後退しつつある区域に護岸と離岸堤を新設する場合は、なるべく護岸を施工する前に離岸堤を設置し、その後に護岸を設置するのが望ましい。
|
離岸堤は、侵食区域の下手側(漂砂供給源に遠い側)から設置すると上手側の侵食傾向を増長させることになるので、原則として上手側から着手し、順次下手に施工する。
|
| 38 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
養浜の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 養浜の施工方法は、養浜材の採取場所、運搬距離、社会的要因などを考慮して、最も効率的で周辺環境に影響を及ぼさない工法を選定する。
2. 養浜材として、養浜場所にある砂より粗い材料を用いた場合には、その平衡勾配が小さいために沖向きの急速な移動が起こり、汀線付近での保全効果は期待できない。
3. 養浜材として、浚渫土砂などの混合粒径土砂を効果的に用いる場合や、シルト分による海域への濁りの発生を抑えるためには、あらかじめ投入土砂の粒度組成を調整することが望ましい。
4. 養浜の陸上施工においては、工事用車両の搬入路の確保や、投入する養浜砂の背後地への飛散など、周辺への影響について十分検討し、慎重に施工する。
|
養浜材として、養浜場所にある砂より粗い材料を用いた場合には、その平衡勾配が小さいために沖向きの急速な移動が起こり、汀線付近での保全効果は期待できない。
|
| 39 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
ケーソンの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. ケーソンの曳航作業は、ほとんどの場合が据付け、中詰、蓋コンクリートなどの連続した作業工程となるため、気象、海象状況を十分に検討して実施する。
2. ケーソンに大廻しワイヤを回して回航する場合には、原則として二重回しとし、その取付け位置はケーソンの吃水線以下で浮心付近の高さに取り付ける。
3. ケーソンの据付けは、函体が基礎マウンド上に達する直前でいったん注水を中止し、最終的なケーソン引寄せを行い、据付け位置を確認、修正を行ったうえで一気に注水着底させる。
4. ケーソン据付け時の注水方法は、気象、海象の変わりやすい海上の作業を手際よく進めるために、できる限り短時間で、かつ、隔室ごとに順次満水にする。
|
ケーソン据付け時の注水方法は、気象、海象の変わりやすい海上の作業を手際よく進めるために、できる限り短時間で、かつ、隔室ごとに順次満水にする。
|
| 40 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
浚渫船の特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. バックホウ浚渫船は、かき込み型(油圧ショベル型)掘削機を搭載した硬土盤用浚渫船で、大規模浚渫工事に使用される。
2. ポンプ浚渫船は、掘削後の水底面の凹凸が比較的大きいため、構造物の築造箇所ではなく、航路や泊地の浚渫に使用される。
3. グラブ浚渫船は、適用される地盤は軟泥から岩盤までの範囲できわめて広く、浚渫深度の制限も少ないのが特徴である。
4. ドラグサクション浚渫船は、浚渫土を船体の泥倉に積載し自航できることから機動性に優れ、主に船舶の往来が頻繁な航路などの維持浚渫に使用されることが多い。
|
バックホウ浚渫船は、かき込み型(油圧ショベル型)掘削機を搭載した硬土盤用浚渫船で、大規模浚渫工事に使用される。
|
スポンサー
|
| 41 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
鉄道路盤改良における噴泥対策工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 噴泥は、大別して路盤噴泥と道床噴泥に分けられ、路盤噴泥は地表水又は地下水により軟化した路盤の土が、道床の間げきを上昇するものである。
2. 噴泥対策工の一つである道床厚増加工法は、在来道床を除去し、軌きょうをこう上して新しい道床を突き固める工法である。
3. 路盤噴泥の発生を防止するには、その発生の誘因となる水、路盤土、荷重の三要素のすべてを除去しなければならない。
4. 噴泥対策工の一つである路盤置換工法は、路盤材料を良質な噴泥を発生しない材料で置換し、噴泥を防止する工法である。
|
路盤噴泥の発生を防止するには、その発生の誘因となる水、路盤土、荷重の三要素のすべてを除去しなければならない。
|
| 42 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
鉄道の軌道の維持管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. レール継目の遊間は、レール温度変化に伴う伸縮を容易にするため設けられており、レールが最高レール温度に達した時に継目ボルトに過大な力がかからないことなどを考慮して設定する。
2. 軌道狂いは、軌道が列車荷重の繰返し荷重を受けて次第に変形し、車両走行面の不整が生ずるものであり、軌間、水準、高低、通り、平面性、複合の種類がある。
3. 車両動揺は、ある範囲の波長の軌道狂いに敏感であるが、列車速度が高くなるに従って、より長い波長の軌道狂いを管理することが重要である。
4. 道床つき固め作業は、軌道狂いを整正する作業であり、有道床軌道において最も多く用いられる作業機械は、マルチプルタイタンパである。
|
レール継目の遊間は、レール温度変化に伴う伸縮を容易にするため設けられており、レールが最高レール温度に達した時に継目ボルトに過大な力がかからないことなどを考慮して設定する。
|
| 43 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
営業線近接工事における保安対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 営業線近接工事においては、工事着手後、速やかに保安確認書、保安関係者届の二つの書類を監督員等に提出しなければならない。
2. 既設構造物等に影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては、異常の有無を検測し、異常が無ければ監督員等に報告する必要はない。
3. 列車の振動、風圧などによって、不安定、危険な状態になるおそれのある工事又は乗務員に不安を与えるおそれのある工事は、列車の接近時から通過するまでの間、一時施工を中止する。
4. 線閉責任者は、当日の作業内容を精査し保守用車・建設用大型機械の足取り、作業・移動区間、二重安全措置、仮置き場所などを図示し、関係する他の線閉責任者に周知徹底させる。
|
列車の振動、風圧などによって、不安定、危険な状態になるおそれのある工事又は乗務員に不安を与えるおそれのある工事は、列車の接近時から通過するまでの間、一時施工を中止する。
|
| 44 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
シールド工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. セグメントの組立ては、トンネル断面の確保、止水効果の向上や地盤沈下の減少などからセグメントの継手ボルトを定められたトルクで十分に締め付けるようにする。
2. 裏込め注入工は、シールド機テール部及びセグメント背面部の止水に役立つため、あらかじめ止水注入を行うものである。
3. セグメントの組立ては、その精度を高めるため、セグメントを組み立ててからテールを離れて裏込め注入材がある程度硬化するまでの間、セグメント形状保持装置を用いることが有効である。
4. 一次覆工の防水工は、高水圧下あるいは内水圧が作用する場合にはシール工を確実にするために、セグメント隅角部に別途コーナーシールを貼り付けることやセグメント隅角部の密着性を確保するためにシームレス加工したものが用いられている。
|
裏込め注入工は、シールド機テール部及びセグメント背面部の止水に役立つため、あらかじめ止水注入を行うものである。
|
| 45 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
鋼構造物の塗装作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 塗料は、可使時間を過ぎると性能が十分でないばかりか欠陥となりやすくなる。
2. 鋼道路橋の塗装作業には、スプレー塗り、はけ塗り、ローラーブラシ塗りの方法がある。
3. 塗装の塗り重ね間隔が短い場合は、下層の未乾燥塗膜は、塗り重ねた塗料の溶剤によってはがれが生じやすくなる。
4. 塗装の塗り重ね間隔が長い場合は、下層塗膜の乾燥硬化が進み、上に塗り重ねる塗料との密着性が低下し、後日塗膜間で層間剥離が生じやすくなる。
|
塗装の塗り重ね間隔が短い場合は、下層の未乾燥塗膜は、塗り重ねた塗料の溶剤によってはがれが生じやすくなる。
|
スポンサー
|
| 46 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
上水道の配水管の埋設位置及び深さに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 地下水位が高い場合又は高くなることが予想される場合には、管内空虚時に管が浮上しないように最小土被り厚の確保に注意する。
2. 寒冷地で土地の凍結深度が標準埋設深さよりも深い場合は、それ以下に埋設するが、埋設深度が確保できない場合は断熱マットなどの適当な措置を講じる。
3. 配水管の本線を道路に埋設する場合は、その頂部と路面との距離は、1.2m(工事実施上やむを得ない場合にあっては、0.6m)以下としないことと道路法施行令で規定されている。
4. 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設する場合は、最小離隔を0.1m以上確保する。
|
配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設する場合は、最小離隔を0.1m以上確保する。
|
| 47 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
下水道の管きょの接合に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. マンホールにおいて上流管きょと下流管きょの段差が規定以上の場合は、マンホール内での点検や清掃活動を容易にするため副管を設ける。
2. 管きょ径が変化する場合又は2本の管きょが合流する場合の接合方法は、原則として管底接合とする。
3. 地表勾配が急な場合には、管きょ径の変化の有無にかかわらず、原則として地表勾配に応じ、段差接合又は階段接合とする。
4. 管きょが合流する場合には、流水について十分検討し、マンホールの形状及び設置箇所、マンホール内のインバートなどで対処する。
|
管きょ径が変化する場合又は2本の管きょが合流する場合の接合方法は、原則として管底接合とする。
|
| 48 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. オーガ方式は、砂質地盤では推進中に先端抵抗力が急増する場合があるので、注水により切羽部の土を軟弱にするなどの対策が必要である。
2. ボーリング方式は、先導体前面が開放しているので、地下水位以下の砂質地盤に対しては、補助工法により地盤の安定処理を行った上で適用する。
3. 圧入方式は、排土しないで土を推進管周囲へ圧密させて推進するため、推進路線に近接する既設建造物に対する影響に注意する。
4. 泥水方式は、透水性の高い緩い地盤では泥水圧が有効に切羽に作用しない場合があるので、送排泥管の流量計と密度計から掘削土量を計測し、監視するなどの対策が必要である。
|
オーガ方式は、砂質地盤では推進中に先端抵抗力が急増する場合があるので、注水により切羽部の土を軟弱にするなどの対策が必要である。
|
| 49 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
薬液注入における環境保全のための管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 大規模な薬液注入工事を行う場合は、公共用水域の水質保全の観点から単に周辺地下水の監視のみならず、河川などにも監視測定点を設けて水質を監視する。
2. 地下水水質の観測井は、注入設計範囲の30m以内に設置し、観測井の深さは薬液注入深度下端より深くする。
3. 薬液注入工事は、化学薬品を多量に使用することが多いので、植生、農作物、魚類や工事区域周辺の社会環境の保全には十分注意する。
4. 地下水等の水質の監視における採水回数は、工事着手前に1回、工事中は毎日1回以上、工事終了後も定められた期間に所定の回数を実施する。
|
地下水水質の観測井は、注入設計範囲の30m以内に設置し、観測井の深さは薬液注入深度下端より深くする。
|
| 50 |
1級土木施工管理技術(平成30年度)問題A |
|
労働時間及び休日に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
|
詳細
|
|
1. 使用者は、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2. 使用者は、原則として労働者に休憩時間を除き1週間について48時間を超えて労働させてはならない。
3. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁に事前に届け出れば制限なく労働時間を延長し、労働させることができる。
4. 使用者は、個々の労働者と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、労働させることができる。
|
使用者は、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
|
スポンサー
|